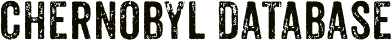タイトル:イスラエルのチェルノブイリ被災地からの移民:健康および社会的適応との関係
著者:レミンニクL. I.
典拠:Social Science & Medicine、54巻、2号、2002年1月、309-317頁。
DOI:http://dx.doi.org/10.1016/S0277-9536(01)00030-2
キーワード:イスラエル、チェルノブイリ、放射線被ばく、(チェルノブイリ被災地からの)移民、不幸の蓄積、健康影響、社会的適応
概要:不幸の累積という概念は、過去のトラウマによる慢性ストレス状態下での移住の研究に有用なツールである。この概念に基づき、本研究では、1990年代にイスラエルに移民したチェルノブイリ原子力災害生存者における放射線被ばくによる長期的健康と心理社会学的影響について調査を行った。ロシア人移民の2グループ(チェルノブイリの被害を受けた地域から来た180人とその他の旧ソ連地域からの移民200人)の間で自己評価による健康状態および社会適応の指標について比較した。半構造化されたアンケートを、ロシア語話者である社会学専攻学生が実施し、定量的および定性的双方の方法で分析した。先行研究と同様、チェルノブイリ被災者の身体的および精神的健康は共に、同じ性別同じ年齢の他の移民と比較して有意に悪い結果を示した。報告された健康問題の大部分は心身に関わる問題だった。調査グループにおいてはうつ病、恥辱感、癌などへの不安がより広く見られた。汚染地域からの移民は保健サービス(従来サービスと代替サービスの両方)をより多く利用する傾向があったが、その質と提供者の態度に対する満足感はより少なかった。健康障害の意識と受入れ国における貧相な共同宿泊施設との間に相関が認められた。他の移民よりも、チェルノブイリ地域からの移民はより深刻な職業的格下げを経験しており、移住の結果により大きな失望感を抱いている。
URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277953601000302
http://www.impact.arq.org/doc/kennisbank/1000011072-1.pdf
タイトル:石と化した廃墟:チェルノブイチ、プリピャチと都市の死
著者:ドブラスチェクP.
典拠:City: analysis of urban trends, culture, theory, policy, action、14巻、4号、2010年、370‐389頁。
DOI:10.1080/13604813.2010.496190
キーワード:チェルノブイリ、都市黙示録、産業遺跡、表現、映画
概要:本稿では、個人的な経験を通して都市の破滅について考えてもらう。記録として自身で撮影した写真を用いて、2007年初頭におけるチェルノブイリ地域における破壊された原子炉と破壊されたプリピャチの建物への訪問を紹介する。プリピャチは大都市はおろか都市でもないかもしれないが、廃墟としてのその規模は戦後においては特筆すべきものである。西側では、廃墟は通常仮想表現、つまり、いわば生身ではない文学や映画においてのみ見られる。プリピャチの廃墟を体験することによって産業の破滅ということに思考が及び、その前例のない規模によって、街全体の、またおそらく文明そのものの破滅といった瞑想にも誘われる。
URL: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13604813.2010.496190#.Ub6JDthLOM0
タイトル:チェルノブイリ:リスクと不確実性とともに暮らす
著者:アボットP., ウォレスC., マティアスB.教授
典拠:Health, Risk & Society、8巻、2号、2006年、105‐121頁。
DOI:10.1080/13698570600677167
キーワード:原子力事故、リスク社会、物語の断絶
概要:1986年のチェルノブイリ原子力事故は「リスク社会」を象徴するタイプの事故の極端な例である。事件の結果は不確定、原因は複雑、今後の展開も予測不能である。その影響を補償することは不可能で、広い範囲に渡る人口に無差別に被害を与えている。本稿では、2003年にロシア、ウクライナおよびベラルーシのチェルノブイリ地域で実施された定性的ケーススタディーに基づいて、地域住民として物語の断絶を経験した人々が経た経験を検証する。これらの分析が示しているのは、情報提供者が彼らの将来をきわめて不確実で予測できないものとして提示する傾向があるということである。彼らは自身がすでに汚染されているかわからないという不確実性に晒され、どこへ行くか何を食べるかについての際どい決定をしなければならない。恐怖、噂そして専門家たちは争うように、災害の実際および潜在的な影響に関する情報を住民に提供するが、提供された情報に対して信頼はあまり寄せられることはなく、意識も少ない。ほとんどの情報提供者は自分たちの生活を続け、リスクがあると分かっていても、「やらねばならぬこと」もしくは「したいこと」をしている。多くの場合、彼らは自身の行動を経済的な事情によるものとする。極貧の中ではたとえ危険な食物でもないよりはましなのだ。本研究では先行研究とは異なり、ソ連邦の崩壊に起因する困難と災害による問題を分離せず、双方が諦観と運命論の根深い感覚の根幹にあるものと捉えて情報提供者における顕著な傾向を検証している。ほとんどの情報提供者は情報、援助、予防措置の不足を政府の責任と見なすが、それらを解消するのに集団行動に訴えることはほとんど皆無である。こうした点は、災害によって被害を受けた集団はその事件に重要な意義を付与し、その結果、関連する政策課題への関心と共にどんどん政治化してくる、と指摘してきた先行研究とは対照的である。
URL:http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13698570600677167#.Ub5-XdhLOM1
タイトル:チェルノブイリの記憶、記念式典そして表現:序章
著者:アルントM.
典拠:Anthropology of East Europe Review、30(1)、現代史センター、ポツダム、レイチェル·カーソンセンター、ミュンヘン、2012年春。
キーワード:チェルノブイリ事故、原子力、記憶、記念行事、ベラルーシ
概要:AEERの本特集はチェルノブイリの記憶、記念行事、そして表現に捧げられている。特集のアイデアは2011年4月ドイツのポツダムにおける国際的研究プロジェクトの最終会議「チェルノブイリ後の政治と社会」で生まれた。この会議は、日本における津波とその後の原子力事故のわずかひと月後、また1986年のチェルノブイリ事故の25周年の数週間前に開催された。
URL:http://scholarworks.dlib.indiana.edu/journals/index.php/aeer/article/viewFile/2009/1959
タイトル:チェルノブイリ・ストーリーとハンガリーの人類学的打撃
著者:ハーパーK. M.
典拠:Anthropological Quarterly、2001年7月、74巻、3号、114-123頁。
キーワード:チェルノブイリ災害、人類学的打撃、ハンガリー
概要:ブダペストにおけるチェルノブイリ記念日には、親の責任、科学的知見、環境リスク、および市民参加に関する創造的な物語が多く生まれた。本論では、1996年4月のチェルノブイリ原子力災害10周年に触発された物語とパフォーマンスを検証する。これらの「チェルノブイリ・ストーリー」については、市民の行為の代替行為であるにも拘らず、活動家たちはその決まったパターナリズムを批判した。壊滅的爆発とその記念日の間の十年はハンガリーの環境保護運動の発展と一致しており、1996年のチェルノブイリの日における社会主義国家からの変容は、結果的にこれまでの年月の間に市民権と市民参加の意義もまた変わってきたということを活動家たちが映し出す機会となったのである。
URL:http://muse.jhu.edu/journals/anthropological_quarterly/toc/anq74.3.html
著者:F.M.ガイドゥク、S.A.イグムノフ、V.B.シャリケヴィチ
典拠:Социальная и клиническая психиатрия (社会的・臨床的精神医学)、1994
概要:専門家の間では広く知られた論文。インターネット上に詳細なし。
著者:K.N.ロガノフスキー、A.N.コヴァレンコ、K.L.ユリイェフ、M.A.ボムコ、E.Yu.アンティプチュク、N.V.デニシュク 他
典拠:Український медичний часопис (ウクライナ医学誌)、2003
キーワード:器質性脳障害、神経心理学、神経精神学、神経生理学、神経画像
概要:脳の放射線感受性の議論がなされている中で、器質性脳障害の立証は重要な地位を占める。本研究の目的は、神経精神学、神経心理学、神経生理学、そして神経画像の調査を通してARS(急性放射線症候群)の遠隔期における器質性脳障害を立証することであった。脳症は、小焦点の神経症状、人格障害、精神病理学的な症状、うつ病や認知障害によって凝縮される。構造的・機能的脳障害。EEG。
URL: http://www.umj.com.ua/article/1029/verifikaciya-organichnogo-urazhennya-golovnogo-mozku-u-viddalenij-period-gostroi-promenevoi-xvorobi
著者:M.O.ボムコ
典拠:修士論文、キエフ、2005
キーワード:遠隔期、器質性脳障害、MR
概要:本研究は、神経学の分野において、ウクライナ国家によるチェルノブイリ事故の処理と人々の防護のためのプロジェクトの一環を成すものである。研究の目的:線量範囲0,05-4,7 Svの被ばくの遠隔期における脳への影響の構造と機能を研究し、チェルノブイリ作業員の器質性脳障害を確認する。
本研究においては、ARSの診断を受けている者を含む、チェルノブイリ清算におけるMR画像の定量分析が初めて行われた。線量範囲0,05-4,7シーベルトの被ばくの遠隔期における器質性脳損傷。
URL: http://librar.org.ua/sections_load.php?s=medicine&id=6920
著者:M.A.ボムコ
典拠:Український медичний часопис(ウクライナ医学誌)、2004
キーワード:イオン化放射線、器質性脳障害、形態学、神経画像
概要:本研究の目的は、MRIを利用し、チェルノブイリ事故の遠隔的影響を受けた脳の形態学的分析をすることである。0.14~4.7グレイの被ばくを受けた79人の作業員を研究。チェルノブイリ事故の影響からではない脳障害を持つ18人の患者も研究対象に。脳水溶における脳構造のコントラスト比、第三脳室のサイズ、側脳室のインデックスボディ、 側脳室の前角と第三脳室ほか。皮質脳経路の大脳半球の萎縮と優位半球の損傷を発見。脳の形態的な異常は0.3グレイ以上の被ばくの影響下に確認される。
URL: http://www.umj.com.ua/article/937/morfometrichna-nejrovizualizacijna-xarakteristika-organichnogo-urazhennya-golovnogo-mozku-u-viddalenij-period-vplivu-ionizuyuchogo-viprominyuvannya-vnaslidok-chornobilskoi-katastrofi