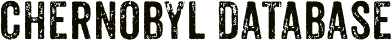タイトル:チェルノブイリ事故後のロシア、ブリャンスク州の乾燥・汚染居住地域における線量評価
著者:アンダーソンK. G., ロードJ.
典拠:環境放射能ジャーナル、85巻、2-3号、2006年、228-240頁。
DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jenvrad.2004.08.019
キーワード:放射線量、放射性セシウム、都市、チェルノブイリ、準備、乾性沈着
概要:核を備える際の必須要件とは、主な事故状況で起こりうる結果をしっかりと予測する能力である。これに関して、いかなる線量の寄与が重要であるか、いかなるのもがそう重要でないかを評価することは肝要である。こうした評価タイプの例として、チェルノブイリ後の初めの17年間の間に、ロシアのブリャンスク州の乾燥・汚染居住地域において受けた線量を推定するためのケーススタディが行われてきた。通り、屋根、外壁および景観の汚染を含む9つの異なる経路を介して受けた線量を推定するための方法論が確立されており、最良の推定値が線量の寄与それぞれに与えられた。一般的には、汚染土壌地域は最高線量の寄与がをあると推定されたが、他の線量、たとえば、汚染された屋根から、あるいは汚染されたプルームの通過時における汚染物質の吸入の寄与の数値は同程度の高さだった。
URL:http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0265931X05002183
タイトル:チェルノブイリのセシウム137の放射性降下物データを使用した食物連鎖モデルのテストおよび対策の影響に関する考察
著者:ウルド·ダダZ.
典拠:全体環境科学、301巻、1-3号、2003年1月1日、225-237頁。
DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0048-9697(02)00285-1
キーワード:チェルノブイリ、セシウム137、食物連鎖、対策、SPADE、線量評価
概要:ロシアで最も汚染された地域で1986-1996年の期間に得られたチェルノブイリのセシウム137のフォールアウト・データが、放射線評価モデルの信頼性をテストするために、IAEAバイオマスプログラム内で使用された。このモデルテストのシナリオには事故後のテスト領域で使用された対策の情報やデータが含まれていた。本報告で紹介するのは、このモデルテストの練習において使用された地上食物連鎖モデルSPADEの予測である。SPADE予測は、差がそれぞれ50倍、200倍に至った豚や野生の果実を除くテストデータと合致した。テストエリアに住む成人男性と女性によるセシウム137の推定摂取量と摂取線量はテストデータとよく一致した。全体的に、SPADEが農業対策とその効果をシミュレートすることが可能なことが証明された。対策のモデル化とは、その「実際の」実装と有効性に対する大きな不確実性を伴う複雑なプロセスであることが分かった。この課題から学んだ教訓は、改善された成果を伴う対策における線量の評価/再構成を今後作成する際に貴重なものとなるであろう。
URL:http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969702002851
タイトル:チェルノブイリ原子炉周辺30kmゾーン内の地上に堆積した99Tcの測定、および事故によって大気中に放出された99Tcの推定
著者:内田滋夫、田上恵子、リュームW., ワースE.
典拠:化学圏、39巻、15号、1999年12月、2757-2766頁。
DOI:http://dx.doi.org/10.1016/S0045-6535(99)00210-6
キーワード:テクネチウム99、チェルノブイリ事故、森林土壌、堆積、セシウム137、移行
概要:チェルノブイリ原子炉周辺30kmゾーンからのサンプルにおけるテクネチウム99を測定した。3つの森林サイトから採取した土壌サンプルにおける99Tcの濃度は有機質土壌層の乾燥重量で1.1~14.1Bq kg -1、鉱質土壌層の乾燥重量で0.13~0.83Bq kg −1の範囲であった。特に有機質層において測定された99Tc濃度の値は、グローバルフォールアウトによる99Tcのそれより1、2桁高かった。有機および鉱質層で測定された堆積合計に基づく99Tcの堆積(Bq m -2)は、10kmゾーン内の130Bq m -2から30kmゾーンの境界線付近における20Bq m -2までの範囲であった。同様に測定されたセシウム137の堆積を考慮してみると、その放射能比は6 × 10 −5~1.2 × 10 −4であることが分かった。約970GBqの99Tcがチェルノブイリ事故によって放出されたと推定される。その数値は炉心における99Tcの総インベントリの2-3%に相当する。
URL:http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653599002106
タイトル:宇宙線の7Beとチェルノブイリ事故のフォールアウトによる137Csの大気沈着
著者:パパステファノC., イオアンニドゥA., ストロスS., マノロポロM.
典拠:全体環境科学、170巻、1-2号、1995年8月18日、151-156頁。
DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0048-9697(95)04608-4
キーワード:大気堆積フラックス、宇宙線放射性核種、チェルノブイリ事故
概要:ギリシャのテッサロニキ(40° 38′N, 22° 58′E)で7年間に渡り(1987年1月~1993年12月)、自然発生した宇宙線起源の7Beとチェルノブイリ事故のフォールアウトによる137Csの大気(対流圏)堆積フラックスを測定した。7Beの年間総沈着フラックスは854Bq/m 2(1987年)と1242Bq/m 2(1992年)の間で変化したが、自然除去および放射性崩壊のためと考えられる有意な減少を示し、原子力施設や核兵器のテストからの新しい放出は見られなかった。7Beの年間平均総沈着速度は0.3cm/s(1988年)から0.8cm/s(1991年)までの間で、一方Cs137はより大きな大気粒子と関連していたため、その値ははるかに高いものであった。空気中の高濃度の7Beはきわめてわずかな太陽活動に関連しており(1987–1988年および1993–1994年)、一方、空気中の低濃度の7Beは活発な太陽活動(1989-1991年)に関連していた。空気中での最大の137Cs濃度は、いくらかの成層圏の入力を反映しつつ1991~1992年の春の間に計測された。空気中のセシウム137濃度値の異常な高度上昇(0.25mBg/m 3に達した)は1990年の夏の間観測された。
URL:http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0048969795046084
タイトル:チェルノブイリ地域における粗い燃料ホットパーティクルの再懸濁
著者:ワーゲンフェイルF., チーリッシュJ.
典拠:環境放射能ジャーナル、52巻、1号、2001年1月、5-16頁。
DOI:http://dx.doi.org/10.1016/S0265-931X(00)00081-3
キーワード:再懸濁、チェルノブイリ放射性降下物、ホットパーティクル、エアロゾルサンプラー、デジタルオートラジオグラフィー
概要:チェルノブイリ30Km立入禁止区域における再懸濁したエアロゾルの測定で、1粒子につき1-12Bqの範囲の放射能をもつ粗い燃料ホットパーティクルが見られた。そのパーティクルは、ひとつの実験中に幾何学的直径が3μm以上、6μm以上、そして9μm以上の三つの燃料粒子サンプルを同時に採取できる、新たに設計された回転アームの衝突体を用いてサンプリングされた。γ-分析後に測定された放射性核種の比率は、事故の際のチェルノブイリ原子力発電所の放射性核種組成および事故後の早い時期に土壌で測定されたホットパーティクルの理論計算とよく一致した。空中のホットパーティクルの粒子数濃度はデジタルオートラジオグラフィーによるものである。風による再懸濁として、1000立方メートル当たり2.6の粗いホットパーティクルの最大濃度と、農業活動中の1000立方メートル当たり36の粗いホットパーティクルを測定した。ひとつのホットパーティクルの幾何学的直径は6-12μmであると推計された。
URL:http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0265931X00000813
タイトル:チェルノブイリからの放射能のイングランドおよびウェールズにおける沈着の評価における気象レーダーの利用
著者:アプシモンH. M., シムスK. L., コリアーC. G.
典拠:大気環境(1967)、22巻、9号、1988年、1895-1900頁。
DOI:http://dx.doi.org/10.1016/0004-6981(88)90078-9
キーワード:湿性沈着、気象レーダー、チェルノブイリ、原子力事故、セシウム137
概要:チェルノブイリ事故からの放射性核種の沈着は沈殿物質の傍受パターンに大きく依存している。本稿では、イングランドとウェールズにおけるセシウム137の湿性沈着を算出するためのRAINPATCHモデルの利用について取り上げている。パフをベースとするこのモデルにより、気象レーダーによって測定された降水量データを空気中の物質の捕捉を決定するのに直接使用できるようになる。何時どこでに関する資料が集められた詳細な空間および時間分解能によって測定値とよく一致するようになっている。使用された全データが潜在的に一度に利用可能であり、このような方法は将来同様の放射性核種を放出する何らかの事故が起こった場合。リアルタイムで有効に適用することができる。
URL:http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0004698188900789
Title: Transfer of radiocesium from uncultivated soils to grass after the Chernobyl accident
Author: Z. Pietrzak-Flis, P. Krajewski, G. Krajewska, N.R. Sunderland
Reference: Science of The Total Environment, Volume 141, Issues 1–3, 25 January 1994, Pages 147-153
DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0048-9697(94)90024-8
Keywords: Radiocesium; Grass; Soil; Transfer factor; Chernobyl
Abstract: Transfer of radiocesium from uncultivated peat, loam and two sandy soils to grass in northeastern Poland was evaluated. Samples of grass and soil were collected from the same area of about 100 m2 in the period from June 1988 to November 1991 twice a year. Grass was sampled from 1 m × 1 m squares by cutting to the plant base. Afterwards core samples of soil were taken from an area of 132.73 cm2. 134Cs, 137Cs and 40K were determined by gamma spectrometry. The average concentration of 137Cs (to 10 cm depth) in the studied areas was in the range from 22.8 ± 2.5 Bq kg−1 to 154.3 ± 13.7 Bq kg−1. The average concentration of this radionuclide in grass varied from 6.76 ± 0.99 Bq kg−1 dry weight (dry wt.) to 152.6 ± 37.4 Bq kg−1 dry wt and depended upon the type of soil. The transfer of radiocesium to grass in the studied soils decreased in the following order: Sand I > peat > Sand II > loam. The results indicated that apart from soil, other parameters also influenced the transfer of radiocesium to grass. It has been found that 134Cs from Chernobyl is more available to grass than 137Cs from nuclear weapon tests.
URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0048969794900248
タイトル:溶解形態でのチェルノブイリの長命放射性核種の地表土壌から河川水への移行能力
著者:天野光、松永武、長尾誠也、半澤有希子、渡辺美紀、上野隆、 小沼義一
典拠:有機地球化学、30巻、6号、1999年6月、437-442頁。
DOI:http://dx.doi.org/10.1016/S0146-6380(99)00028-5
キーワード:ストロンチウム90、セシウム137、超ウラン元素、スペシエーション、地表土壌、流出、溶解した有機材料、フルボ酸、限外ろ過、チェルノブイリ30キロゾーン
概要:水文流出は、表面環境に堆積した放射性核種が微粒子および溶解双方の形態で広く移行する主要なプロセスの一つである。本稿が焦点を当てるのは、溶解形態でのチェルノブイリの長命放射性核種の地表土壌から河川水への移行能力である。第一に、チェルノブイリ原子力発電所(NPP)周辺の立入禁止区域(30キロゾーン)内の川沿いの手付かずの地表土壌において、放射能汚染の特性を検証するために、放射性セシウム、ストロンチウムおよびPuやAmといった超ウラン同位体の濃度および分化を調査した。手付かずの土層における表面の最上部にはほとんどすべての放射能が存在していた。土壌中のストロンチウム90は水溶性および交換可能画分において最も高いと推定され、溶解した画分として河川水に容易に移行するものであった。Puの同位体およびAM241は遊離腐植酸および遊離フルボ酸画分の主要な放射性核種である。第二に、表面土壌から河川水への流出成分における溶解割合を推定するために、サハン川付近の地表土壌を雨水の類似物として蒸留水で抽出した。濾過の手順の後、抽出された水を、1万Da超および以下の分子量画分を分離する限外濾過法で処理した。それぞれの画分における放射能と腐植を含む有機材料の特性を測定した。溶解した有機画分のほとんどが1万Da以下に存在したという事実にも拘らず、ほとんどのPuとAmは1万Daを超える分子量画分に存在した。このことは、PuやAmといった超ウラン元素が河水の浸出液におけるフルボ酸のように移行性の高分子量物質と関連していることを意味している。
URL:http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0146638099000285
タイトル:チェルノブイリ原子力発電所に隣接した土壌中のγ放射性核種の化学形態
著者:クリャストリンA. L., シチェグロフA. I., ティホミロフF. A.
典拠:全体環境科学、164巻、3号、1995年3月30日、177-184頁。
DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0048-9697(95)04464-C
キーワード:放射性核種、チェルノブイリ原子力発電所、セシウム、土壌
概要:砂を含む森林土壌、砂を含む泥炭土牧草地、砂を含むローム牧草地のサンプルが、チェルノブイリ原子力発電所(ChNPP)周辺30Kmゾーン内の異なる地点で採取された。サンプルは水と0.1 Nの酢酸アンモニウム溶液で抽出した。抽出物のγ放射性核種と安定した陽イオン含有量を測定した。0-10 cmの土壌層に存在する移行性放射性核種の全コンテンツは、放射性核種と土壌の種類にもよるが、この層の全放射性核種含有量の0.5〜5%を占めた。水溶性放射性核種は0-5 cmの層でのみ見られた。置換性の放射性核種としては、概して0-5cmおよび-5-10cmの層における放射性セシウムが挙げられる。有機ミネラル層中の置換性のセシウム137のコンテンツは安定した交換可能な陽イオンと有機物含有量の合計にほぼ反比例していた。森林植生が土壌から移行した放射性セシウムの大きな割合を占めている。
URL:http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/004896979504464C
タイトル:耕作地内の土壌再分配評価のためのチェルノブイリ由来物の応用
著者:ゴロソフV.
典拠:土壌・耕作研究、69巻、1-2号、2003年2月、85-98頁。
DOI:http://dx.doi.org/10.1016/S0167-1987(02)00130-7
キーワード:チェルノブイリ、土壌再分配、浸食、メソッド
概要:1986年4-5月にヨーロッパの広大な地域がチェルノブイリ由来物で汚染された。本稿では、中央ロシア高地北部のチャソヴェンコフ・ヴェルフ集水域の1ヘクタールの耕地内における、その後の放射性降下物の再分配の詳細な調査について報告する。基準インベントリの調査に特に注意を払った。ランダムな空間的変動は平らな河間地域内の未耕作および耕作部分と同様であることがわかった。体系的な空間変動は簡単な除去を行った比較的短い(200m)地形のユニットに必ず伴うものではない。チェルノブイリの技術を使った調査フィールド内の土壌の再分配パターンの分析によって、土壌の損失/獲得の領域を識別することが可能であることが示された。チェルノブイリ事故からわずか12年しか経っていないため、このパターンはフィールド全体の土壌の再配分を反映していない。このメソッドに基づく正味の侵食速度は、調査フィールドで直接測定された土壌損失に匹敵する。
URL:http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167198702001307