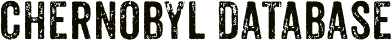Title: Childhood thyroid diseases around Chernobyl evaluated by ultrasound examination and fine needle aspiration cytology.
Author: Ito M, Yamashita S, Ashizawa K, Namba H, Hoshi M, Shibata Y, Sekine I, Nagataki S, Shigematsu I. Department of Pathology, Nagasaki University School of Medicine, Japan.
Reference: Thyroid. 1995 Oct;5(5):365-8.
doi:
Keywords:
Abstract: Screening by ultrasound examination and fine-needle aspiration cytological biopsy (FNA) was conducted in five regions in Belarus, Ukraine, and Russia to investigate the prevalence of childhood thyroid diseases around Chernobyl. Gomel, Zhitomir, Kiev, and the western area of Bryansk are the administrative regions where severe radioactive contamination occurred. The subjects from Mogilev, where contamination was relatively low, served as controls. Among 55,054 subjects (26,406 boys and 28,648 girls), the prevalence of ultrasonographic thyroid abnormalities such as nodule, cyst, and abnormal echogenity was significantly higher in the regions with severe contamination than in Mogilev. Of the 1,396 children showing echographic thyroid abnormalities 197 were selected for FNA, and a sample was successfully obtained for diagnosis from 171 (51 boys and 120 girls) of the 197 subjects. The aspirate was insufficient for diagnosis in the remaining 26 subjects. Thyroid cancer was encountered in four children (2.3%) from the contaminated regions, two children being from Gomel. The other thyroid diseases were follicular neoplasm, 6.4%; adenomatous goiter, 18.7%; chronic thyroiditis, 31.0%; and cyst, 24.0%, suggesting that a major cause of thyroid nodularity is nonneoplastic changes, mainly chronic thyroiditis and cysts. These results will serve as an important data base for further analyses and suggest that childhood thyroid diseases, including both neoplasms and immunological disorders, are consequences of radioactive fallout.
URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8563473
タイトル:チェルノブイリ原発事故以降の甲状腺癌-1991~1992年ベラルーシ共和国の病理学的研究84の症例
著者: ニキフォロフ、グネップ
典拠:Cancer.- 1994
doi:
キーワード:
概要:ベラルーシ共和国では、1990年から急激に甲状腺癌が増加。ベラルーシ共和国の5~14歳の形態的・臨床的な84の症例。腫瘍の潜伏期間-4~6年(平均5.8年)。
URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8033057
タイトル:対流圏と下部成層圏における核兵器とチェルノブイリ・デブリ
著者:コヴナツカL., ヤオロウスキZ.
典拠:全体環境科学、144巻、1-3号、1994年4月29日、201-215頁。
DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0048-9697(94)90439-1
キーワード:放射性核種、対流圏、成層圏、核実験、チェルノブイリ放射性核種、ストロンチウム90、セシウム137、対流圏、成層圏、セシウム134、核実験
概要:高高度における航空機によるエアロゾルのサンプリングが、ポーランド上空15Km以下の4-7段階において実施された。1973-1991年で102のストロンチウム90、セシウム134およびセシウム137の垂直濃度プロファイルと、83のセリウム144の83のプロファイルが測定された。1980年のサブメガトン級の核実験の1年間後、セシウム137はほぼ完全に成層圏から削除されていた。チェルノブイリ・デブリは事故後3日目から1991年末まで成層圏で見られた。1986年5月においては、成層圏の高度におけるセシウム134とセシウム137の濃度は、地上レベルと3キロの間の約0.5%に達した。1987年から1991年の間に、下部成層圏におけるチェルノブイリ放射性セシウムの滞留時間は核実験によるデブリのそれとは異なり段階的に増加した。放射性セシウムの垂直濃度分布と長い滞留時間は、穏やかな気象経過がチェルノブイリ・デブリを事故後直ちにまた長時間に渡って下部成層圏に運んだことを示している。同様の静止性のプロセスが陸海の表面から高高度まで膨大な量の再懸濁した粒子状の有機物を運び込み、成層圏の化学的作用と関わっている可能性があると仮定される。
URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0048969794904391
タイトル:チェルノブイリ事故後のヨーロッパの大気中放射能の測定
著者:ラースF., グラツィアーニG., スタナスD., ジラルディF.
典拠:大気環境、パートA., 一般的トピック、24巻、4号、1990年、909-916頁。
DOI:http://dx.doi.org/10.1016/0960-1686(90)90293-V
キーワード:チェルノブイリ、空気中濃度、LRT、セシウム134/セシウム137
概要:チェルノブイリ原子力発電所事故による大気中の一連の放射能の包括的なヨーロッパ・データを提示する。放出開始後の最初の2週間における、ヨウ素131、セシウム134。セシウム137の微粒子レベル(85か所)および全ヨウ素131(10か所)レベルを出した。全てのデータはコンピュータのデータベースに収められている。ヨーロッパ上空におけるチェルノブイリ雲の初の通過は、一日の濃度を整合性を以て出すため、各場所における時間履歴を再平均化した後にマッピングされた。セシウム134/セシウム137比率が分析した結果、1239のサンプルから計算された「ヨーロッパ」の平均比率は0.55であった(標準偏差0.25)。
URL:http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/096016869090293V
タイトル:スウェーデン北部におけるチェルノブイリ事故前後のトナカイとカワカマスの筋肉組織における放射性セシウム。スウェーデン環境試料バンクからの組織サンプルに基づく遡及的研究
著者:フォルベルクS., OdsjöT., オルソンM.
典拠:全体環境科学、115巻、3号、1992年4月30日、179-189頁。
DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0048-9697(92)90328-P
キーワード:放射性セシウム、トナカイ、カワカマス、チェルノブイリ、環境試料バンク
概要:1986年4月のチェルノブイリ事故後、放射性核種の著しい堆積がスウェーデンの東部、中央および北西部で地域的に発生した。局所的には、放射性セシウム降下物は大気中における核実験の残存物を数倍上回っていた。1960年代の終わりから、毎年異なる地域で収集された様々な植物や動物の種からの器官のサンプルがスウェーデン環境試料バンク(ESB)に保存されてきた。本研究では、ESBからのサンプルを放射能汚染の遡及的研究のために使用した。ESBに保存されていたトナカイとカワカマス(ノーザンパイク)の筋肉組織におけるセシウム134とセシウム137の放射能を測定した。トナカイはスウェーデン北部の3地域で、カワカマスはそのうちの1地域でサンプルが毎年採取されている。チェルノブイリ事故の前に収集された資料においては、新鮮重におけるセシウム137レベルはトナカイで57–180 Bq/kg、カワカマスで14–24 Bq/kgだった。これらのレベルは以前の核爆弾の実験と関連している。チェルノブイリ以前の期間(1971~1986年)にはカワカマスにおいて有意な減少が現れた。チェルノブイリ後のサンプルにおけるセシウム137の負荷は、最北地域における元のレベルに等しい量から最南端地域における最大で80倍高い値にいたるまで様々だった。記録された最高値はトナカイにおける18,425Bq/kgだった。チェルノブイリ放射性降下物以降のトナカイの地理的変動は、1986年5月に行われた航空機調査で推定された堆積物のパターンと一致していた。1987年に捕獲されたカワカマスにおける「新しい」および「古い」放射性セシウム負荷の比率は、湖の堆積エリアに放牧されたトナカイにおける対応比率(それぞれ33および19)に近づいた。
URL:http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/004896979290328P
タイトル:チェルノブイリ事故の影響を受けた農村部:放射線被曝と修復戦略
著者:ヤコブP., フェセンコS., ボグデヴィチI., カシュパロフV., サンジャノヴァN., グレベンシコヴァN., イサモフN., ラザレフN., パノフA., ウラノフスキーA., ジュチェンコY., ジュルバM.
典拠:全体環境科学、408巻、1号、2009年12月15日、14-25頁。
DOI:http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2009.09.006
キーワード:セシウム、チェルノブイリ、電離放射線、リハビリテーション、修復
概要:本研究の主要目的は、チェルノブイリ事故の影響をいまだ受けている農村部における最適化された改善戦略を導き出すための国際的合意を得た方法論を開発することと、ベラルーシ、ロシアおよびウクライナの被災3カ国における放射線状況の概要を描き出すことである。研究対象集落の定義は、2004年時点で住民が1万人未満で公式線量推定値が1mSvを超えていることとされた。人口、現在の農業活動、土壌や食品の汚染および以前適用された是正措置のデータが、そうした541研究対象集落ごとに収集された。内部放射線による年間実効線量の計算が、全身カウンタ測定に関する広範なデータセットと共に検証された。2004年の計算によると、290の研究対象集落で有効線量が1mSvを超え、これらの集落での集団線量は約66人·シーベルトに達した。以下の6つの是正措置が検討された。すなわち、草原の根本的改善、牛へのヘキサシアノ鉄酸の適用、屠殺前の豚への汚染されていない飼料の供給、ジャガイモ畑へのミネラル肥料の施肥、汚染された森林の産物に関する情報キャンペーン、人口密集地域における未汚染土壌による汚染土壌の入れ替え、である。
URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004896970900850X
タイトル:ウクライナ、チェルノブイリ付近の河川におけるストロンチウム90の実質的な供給源地
著者:フリードR., スミスL., ブガイD.
典拠:汚染水文ジャーナル、71巻、1-4号、2004年7月、1-26頁。
DOI:http://dx.doi.org/10.1016/j.jconhyd.2003.07.002
キーワード:チェルノブイリ、水文汚染物質移行、面源、土壌汚染、ストロンチウム90
概要:面源汚染物質の影響を受けた河川を回復させるには、河川に汚染物質を供出している流域内のエリアおよび河川の汚染物質の移行経路の双方を理解しておく必要がある。1998~2002年の間、Borschi流域(ウクライナのチェルノブイリ原発の南3kmの小さな(8.5km 2)流域)におけるストロンチウム90の移行を調査した。流域全体において不均一に広まっている燃料粒子は、燃料マトリックスから風化し放出されたストロンチウム90である。不動の核分裂生成物ユーロピウム154と比較して査定されたストロンチウム90の枯渇は水路と湿地堆積物において発生している。水路堆積物におけるストロンチウム90は深さに応じて均一に枯渇している。湿地堆積物中には上部10㎝および10〜25cmの深さにおける蓄積部分の枯渇ゾーンがある。ストロンチウム90の枯渇の推定は、主要水路にストロンチウム90を排出している実質的な供給源地をマッピングするのに用いられている。実質的な供給源地には、水路底の堆積物、流域の中央領域における湿地、湿地に囲まれた定期的浸水土壌が含まれる。実質的な供給源地からの総枯渇は36±7×10 10Bqと推定される。1999-2001年の河川の流量と水質の観察に基づくと、流域からのストロンチウム90の年間除去率は1.4±0.2×10 10、もしくは年間インベントリの1.5%と推定される。チェルノブイリ事故後15年間を外挿法で推定すると、最終値はストロンチウム90/ユーロピウム154比に基づく供給源地の推定枯渇量と合致する。全流域を考慮したストロンチウム90の年間浸出率は0.2%だが、実質的な供給源池を考慮したストロンチウム90の浸出率はそれより一桁高い。流域におけるストロンチウム90の放出のほとんどは0.62km 2ある実質的な供給源地領域。もしくは流域面積の7%に由来している。
URL:http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169772203002225
タイトル:チェルノブイリ事故の放射線影響を軽減する効果的手段としての農業生産の対策
著者:アレクサヒンR. M.
典拠:全体環境科学、137巻、1-3号、1993年9月2-4日、9-20頁。
DOI:http://dx.doi.org/10.1016/0048-9697(93)90374-F
キーワード:チェルノブイリ事故、農業、セシウム137、放射能汚染、対策
概要:1986年のチェルノブイリ事故をきっかけに、農業における様々な保護対策の実施が人口中の総放射線量を減少させるのに最も効果的な手段となっている。土壌汚染除去による外部放射線の減少は、コストもはるかに少なく効果的である。農業対策の結果、内部用量は約3倍減少した。ロシアでは、これらの対策の結果、セシウム137の蓄積が耕地作物中では約2.3倍、牧草地では約2.8倍減少した。牧草中の放射性セシウムの減少が最も重要な要因の一つで、これによって牛乳(人間の食事中の放射線量の主な源)中のセシウム137が減少したのである。放牧地で使用された対策には、すき起こし、石灰処理、肥料の応用等が含まれる。植物の作物におけるセシウム137は栽培作物の種類を変更することによって5〜10倍減少させることができる。自然の草地や牧草地、処置の恩恵を受けていない耕地土壌においてはセシウム137の植物への取り込みは時間と共に減少する。農業における様々な保護対策の効果は事故被害を受けた地域で評価されている。
URL:http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/004896979390374F
タイトル:チェルノブイリ原子炉30kmゾーンの森林土壌中のテクネチウム99の濃度レベル
著者:内田滋夫、田上恵子、ヴィルトE., リュームW.
典拠:環境汚染、105巻、1号、1999年4月、75-77頁。
DOI:http://dx.doi.org/10.1016/S0269-7491(98)00210-3
キーワード:テクネチウム99、チェルノブイリ事故、森林土壌、セシウム137、ICP-MS
概要:チェルノブイリ原子炉周辺30kmゾーン内の3つの森林サイトから収集した表面土壌サンプルにおけるテクネチウム99(99Tc)濃度を測定した。燃焼装置内のTcの揮発とトラップ、抽出クロマトグラフィー樹脂によるTcの精製、そしてICP-MSによる測定から成る簡単かつ迅速な分析方法が測定のために用いられた。サンプル中の99Tc濃度は、空気乾燥した土壌ベースで1.1~14.1Bq kg -1の間であった。チェルノブイリ原子炉周囲の土壌中の核種の放射能は、事故での被害がより少なかった他の地域に比べて1桁から2桁大きかった。土壌中の99Tcとセシウム137放射能比率は3.7×10 −5~1.3×10 −4程度として計算した。
URL:http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749198002103
タイトル:チェルノブイリ原子力発電所周辺のいくつかの地域から選ばれた無脊椎動物におけるプルトニウム、セシウム137、ストロンチウム90
著者:ミエテルスキJ. W., マクシモヴァS., シュワウコP., ウヌクK., ザグロズキP., ブワジェイS., ガカP., トマンキエヴィツE., オルロフO.
典拠:環境放射能ジャーナル、101巻、6号、2010年6月、488-493頁。
DOI:http://dx.doi.org/10.1016/j.jenvrad.2008.04.009
キーワード:プルトニウム、ストロンチウム90、セシウム137、チェルノブイリ、無脊椎動物、生物相の放射能汚染
概要:チェルノブイリ除外ゾーンにおける高度汚染地域で収集された甲虫類、アリ、クモやヤスデといった20以上の陸生無脊椎動物のサンプル中におけるセシウム137、ストロンチウム90とプルトニウムの放射能濃度の結果が示されている。サンプルの大部分はベラルーシで、いくつかはウクライナでも集められた。他の三つのサンプルは汚染度の低い領域で収集された。その結果、7つのサンプルはセシウム137の放射能濃度が100kBq/kg(灰重量– a.w.)を超えていることが分かった。この同位体の最大放射能濃度はアリ(Formica cynerea)において測定された1.52±0.08 MBq(a.w.)であった。ストロンチウム90に関する7つの結果は100kBq/kg(a.w.)を超え、主にヤスデで見られた。比較的高いプルトニウムの放射能濃度は数種のアリとセンチコガネで見られた。放射能の分析によって種の間の放射性核種の移行の違いが示された。多変量データセットの相関構造を明らかにするため、部分最小二乗法(PLS)を用いた。PLSモデルの結果、動物体内における放射性セシウムの高い放射能濃度は、わらなどの表面に住む比較的小さな生き物に主に見られることが分かった。対照的に、高いストロンチウム放射能濃度は、混合栄養の習慣と適度な寿命を持つ、わらなどの中で生活する生き物に見られる。プルトニウムに関してははっきりした結論が出なかった。
URL:http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0265931X08000696