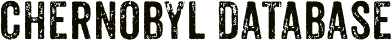タイトル:ヨウ素131治療を受けた甲状腺がん患者における放射線誘発DNA損傷分析へのアルカリ性の単細胞ゲル電気泳動(SCGE)アッセイの利用
著者:S. グティエレス、E. カルボネル、P. 、ガルフレ、A. クレウス、R. マルコス
典拠:突然変異研究/遺伝毒性と環境変異誘発、413(2)、111‐119頁、1998年3月。
デジタルオブジェクト識別子:10.1016/S1383-5718(98)00010-2
キーワード:ヒト血液細胞、コメットアッセイ、甲状腺癌患者、ヨウ素131 ヨウ化ナトリウム
概要:…結節性甲状腺腫や甲状腺がんを伴う…直後におけるチェルノブイリ地域におけるリクビダートル…チェルノブイリ労働者の調査は…示した…甲状腺への蓄積、この腺は…を使用した甲状腺がん患者の同じグループ…
URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1383571898000102
タイトル:放射線被ばく後の甲状腺がん
著者:C. ルビノ、A. F. カイユ、F. ド・ヴァテール、M. シュルンベルジェ
典拠:ヨーロッパがんジャーナル、38(5)、645-647頁、2002年5月。
デジタルオブジェクト識別子:10.1016/S0959-8049(02)00009-6
概要:…1986年のチェルノブイリ事故の結果…チェルノブイリの半径…キロ:いかなる甲状腺がんも見られなかった…チェルノブイリに関係する…甲状腺への放射線量…甲状腺がん関連の死亡率…
URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959804902000096
タイトル:ポスト・チェルノブイリNIS甲状腺組織、核酸およびデータバンク、および統合的研究
著者:G. A. トーマス
典拠:国際学会シリーズ、1234、127‐134頁、2002年5月。
デジタルオブジェクト識別子:10.1016/S0531-5131(01)00603-3
キーワード:チェルノブイリ、甲状腺がん、組織リソース
概要:チェルノブイリ事故が起こった時19歳以下だった、ベラルーシ、ウクライナ、ロシアの汚染地域の居住者における甲状腺患発生率の増加により、放射線が病因とされるヒトの腫瘍に関する科学的研究は貴重な機会を与えられた。それは患者の利益に関わるのみならず、将来の事故に備えての情報、また被災者の予後の改善にとっても重要である。そこで我々は初の国際協力として、 新独立国家チェルノブイリ組織バンク(NISCTBの名で知られる)を組織した…
URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0531513101006033
タイトル:MTS-N (LiF:Mg, Ti) およびMCP-N (LiF:Mg, Cu, P)熱ルミネセンス検出器に基づく長期的環境モニタリング
著者:M. ブザノウスキ、P. オルコ、B. オブリク、E. ルィバ、A. ノワク
典拠:放射線測定、38巻、4-6号、821-4頁、2004年8-12月。
デジタルオブジェクト識別子:10.1016/j.radmeas.2004.01.023
キーワード:熱ルミネセンス、TLD、LiF、環境測定
概要:標準的なMTS-N (LiF:Mg, Ti) および高感度の熱ルミネセンスLiF:Mg,Cu,P (MCP-N) 検出器を使用した環境放射線モニタリングシステムが、クラクフの核物理研究所(INP)区域の放射線被ばくを制御するために適用されている。MTS-N 検出器を使用しての初の環境測定は1970年に5か所で開始し、チェルノブイリ事故の間も6地点において継続した。1987年3月に手動TLリーダーで読みだされる高感度MCP-N検出器がINPにおけるサービスに初めて導入された。1992年からINP区域を超える60か所が、カード内臓のMTS-N検出器に基づく自動TLDシステムを使用しての四半期ごとの線量率測定のために選ばれた。2002年にはMTS-N検出器は高感度MCP-Nペレットに置き換えられた。
URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1350448704000290
タイトル:ザグレブ(クロアチア)の空気中の放射性物質の長期的調査
著者:Z. フラニッチ、G. マロヴィッチ、J. センカー
典拠:大気研究、89巻、4号、391-5頁、2008年9月。
デジタルオブジェクト識別子:10.1016/j.atmosres.2008.03.005
キーワード:放射能、セシウム137、ベリリウム7、チェルノブイリ事故、実効線量
概要:クロアチアのザグレブ市における、天然に存在する放射性核種、核兵器によって生産される放射性核種、原子炉から放出される放射性核種の分布と動態に関する研究が、1960年代初頭からクロアチアにおいて、人間環境の放射能汚染のための監視プログラムの一環として行われてきた。本論文では、チェルノブイリ事故後のザグレブ市における人工のセシウム137と自然発生のベリリウム7の長期調査について取り上げられている。チェルノブイリ原発事故によって、1986年のみセシウム137の放射能濃度の大幅な増加が起こったが、それはその後数年の内に迅速にチェルノブイリ以前の値に減少した。1987年1月から1990年12月までのポスト·チェルノブイリの期間中観察されたセシウム137の空気中の平均滞留時間は1.0年と推定された。この期間中観察された放射性降下物中のセシウム137の平均滞留時間は0.9年と推定された。1987年から2004年までの空気中のベリリウム7の平均放射能濃度は、(5.4±2.8) × 10− 3 Bq m− 3であった。測定されたベリリウム7の放射能濃度は、通常7月に最高値が測定されるという季節的動向を示した。
URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169809508000689
タイトル:子宮内あるいは誕生後の慢性被ばくの後、精巣ステロイドはチェルノブイリ放射性降下物のセシウム137によって変わらない。
著者:E. グリニャール、Y. グエグエン、S. グリソン、I. ダブリノー、P. ゴーメロン、M. スイディ
典拠:生物学レンダリング報告、333巻、5号、416‐423頁(8頁)、2010年5月。
デジタルオブジェクト識別子:10.1016/j.crvi.2010.02.003.
キーワード:精巣 – 生理学、セシウム – 同位体、ステロイドホルモン – 合成、チェルノブイリ原発事故、チェルノブイリ、ウクライナ、1986年、遺伝子発現、汚染(技術)、実験動物としてのラット
概要:精巣は放射性核種を含む汚染物質に特に敏感である。チェルノブイリ原発事故後、その放射性核種のいくつかが放出され環境内に広がった。その後、子どもたちは内分泌系の不具合を訴えた。それらの不具合がセシウム137に被ばくしたためかどうかを判定するために、子宮内または誕生後のラットの精巣ステロイド上に対する低用量のセシウム137を含む慢性汚染の影響を検討した。汚染は9か月間続いた。子宮内もしくは誕生後の汚染後、ホルモン(17βエストラジオール、テストステロン、卵胞刺激ホルモン、黄体形成ホルモン)の循環レベルにおいてはいかなる変化も観察されなかった。精巣ステロイド合成に関与するいくつかの遺伝子の発現が影響を受けた(cyp19a1, fxr, sf-1)が、タンパク質の発現または活性の変化は無かった。成長中の生物は、この事故後の放射能でセシウム137汚染によって分子レベルで影響を受ける可能性がある。
URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1631069110000466
タイトル:ウクライナのチェルノブイリの環境に生息するハタネズミ、ヨーロッパヤチネズミの集団におけるミトコンドリアDNA制御領域のハプロタイプのばらつき
著者:J. K. ウィクリフ、Y. V. ドゥニナ-バルコフスカヤ、S. P. ガスチャク、B. E. ロジャース、R. K. チェッサー、K. ロナルド、M. ボンダルコフ、R. J. ベイカー
環境毒性学&化学、25巻、2号、23-23頁(1頁)、2006年2月。
デジタルオブジェクト識別子:10.1897/05-327R.1
キーワード:チェルノブイリ、ハタネズミ、ミトコンドリア、 DNAの多様性、放射線
概要:ハタネズミ、ヨーロッパヤチネズミの標本は、ウクライナのチェルノブイリの放射性環境および非放射性サイトから、1997年以降毎年サンプリングされてきた。被ばくしたハタネズミは増加したミトコンドリアDNAのハプロタイプ(h)およびヌクレオチド多様度(ND)を示し、それは超可変制御領域において観察された(1997‐1999年)。増加した母系の突然変異率、ソース・シンク関係、もしくは両方が、この変化の仮説として提出された。追加年(2000年、2001年)のサンプルもこの経時的研究に組み込まれている。増加した突然変異率は増加したhと関連しているという仮説を検証するため、ウクライナ外部からの、あるいは他の種のハタネズミのハプロタイプにおいては観察されなかった新たな置換の系統発生状況におけるDNA配列について調べた。そのような新規な置換は原位置の突然変異事象から生じるかもしれず、放射性環境からのサンプルに大幅に限定した場合、これらの地域で増加した母系の突然変異率を裏付けている。この基準に合う唯一ユニークな置換は非汚染サイトで見られた。その他の全ての置換はハタネズミのハプロタイプおよび他の種において見られた。増加した母系の突然変異率は、ウクライナ北部で観察されたhおよびNDの傾向を説明する形では現れていない。生態学的ダイナミクスを調べる研究は、汚染地域におけるhのレベルの増加の理由と意義を明確にするであろう。
URL: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1897/05-327R.1/abstract
タイトル:環境(北極と南極を含む)中の放射能:2005年10月2‐6日フランス、ニースにおける国際会議より
著者:P. ストランド、J. ブラウン
典拠:環境放射能誌、96巻、1‐3号、1‐5頁、2007年7月‐9月。
デジタルオブジェクト識別子:10.1016/j.jenvrad.2007.01.014
キーワード:放射線モニタリング。放射能汚染、放射能測定、リスクマネジメント、北極領域、南極領域、放射生態学、環境放射能、生態系、経験的データ、モデリングツール、チェルノブイリ事故、自然発生の放射性物質の技術的増強、TENORM、環境保護、放射能測定、放射能のモニタリング、リスクアセスメント、リスクマネジメント
概要:経験的データの分析とモデリングツールの使用を通しての、生態系における放射性核種の挙動理解および人と環境の放射線被ばく後の影響の研究は、放射生態学科学の伝統的主流であった。1950年代後半から1960年代初頭に集中的な大気核実験が続いた後、環境における放射能によるグローバルな汚染と放射性核種の移送および破滅についての最初の洞察を科学者たちが提出した。それらの初期研究の間に、いくつかの放射性核種、特にセシウム137とストロンチウム90は、摂取によってヒト集団に放射能の潜在被ばくをもたらす陸生や水生食物連鎖を介して比較的容易に移送されることが明らかになった。
URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0265931X0700063X
タイトル:ロシアのイプチ川流域におけるチェルノブイリの放射性降下物のセシウム137のデータを用いたモデル検査
著者:K. M. ティーセン、T. G. サジキナ、A. I. アポスタエイ、M. I. バロノフ、J. クロフォード、R. ドメル、S. V. フェセンコ、V. フィリストヴィチ、D. ガレリュ、T. ホンマ、B. カニャル、P. クラエウスキ、A. I. クリシェフ、I. I. クリシェフ、T. ネドヴェカイト、Z. ウルド·ダダ、N. I. サンジャロヴァ、S. ロビンソン、K. -L. ショブロム
典拠:環境放射能誌、84巻、2号、225‐44頁、2005年。
デジタルオブジェクト識別子:10.1016/j.jenvrad.2004.10.016
キーワード:セシウム137、モデル検査、線量再構築、チェルノブイリ
概要:1986年のチェルノブイリ事故以後10年に渡って集められたデータによって、陸上および水生環境の汚染用のコンピュータモデルの信頼性をテストするユニークな機会が得られた。イプチ川のシナリオはBIOMASS (生物圏モデル化と評価手法)プログラムの線量再構築ワーキンググループによって使用された。テストエリアは事故後のロシアで最も高度に汚染された地域の一つで、セシウム137の平均的な汚染密度が80万Bq m−2 、局地的には150万Bq m−2まで上り、モデリング演習においてはテスト領域で実行したさまざまな防御対策を講じなければならなかった。運動中に遭遇した困難としては、テスト領域の不均一な汚染を考慮してのデータの平均化、土壌中のセシウム137の生物学的利用能における下降移行と変化のシミュレート、そして対抗策の有効性のモデル化が挙げられる。モデル予測の精度は、入力された情報の解釈、パラメータ値の選択、および不確実性の処理における参加者の経験および判断に、少なくとも部分的には依存している。
URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0265931X05001499
タイトル:スイス・アルプスにおけるセシウム137測定のための原位置測定の応用
著者:M. シャウブ、N. コンズ、K. ミュースバーガー、C エルウェル
典拠:環境放射能誌、101巻、5号、369‐76頁、2010年5月。
デジタルオブジェクト識別子:10.1016/j.jenvrad.2010.02.005
キーワード:NaI検出器、GeLi検出器、アルプス、原位置測定、フィールド適用
概要:セシウム137の保有量の確定は土壌の安定性に関する情報を得るためにしばしば利用されてきた。土壌の安定性は、生態系の安定性が密接に土壌のそれに関わるような山のシステムにおいては非常に重要である。険しい高山環境におけるセシウム137の原位置測定は不足している。ほとんどの研究は耕地でゲルマニウム(Ge)検出器を用いて行われてきた。ヨウ化ナトリウム(NaI)検出器システムは安価でフィールド機器を処理するのも容易であるが、険しい高山環境での有効性はまだテストされてない。本研究では、土壌のセシウム137のガンマ線のGeLi検出器を使った実験室測定とNaI検出器を使った原位置測定の比較を、高濃度のセシウム137を持つ高山流域において行った。
URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0265931X10000354